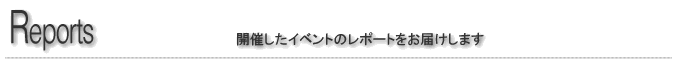
第7回ロタブルー・トライアスロン大会!
(2000年11月18日開催)
The 7th Rota Blue Triathlon !!
日本航空機内誌「winds」2001年9月号に掲載されたレポート
|
初めてのトライアスロン
|
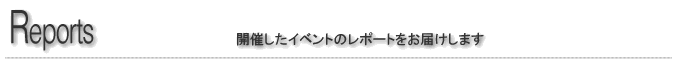
第7回ロタブルー・トライアスロン大会!
(2000年11月18日開催)
The 7th Rota Blue Triathlon !!
日本航空機内誌「winds」2001年9月号に掲載されたレポート
|
初めてのトライアスロン
|